近年、世界の経済成長の減速、金利上昇、物価高など、多くのリスク要因が言及される中で、「リセッション(景気後退)」が現実味を帯びています。rbcwealthmanagement.com+3russellinvestments.com+3capitalgroup.com+3これに伴い、インデックス投資を行っている個人投資家にとっては、従来の“ほったらかしで良い”という認識に加えて、景気後退局面ならではの注意点と“急反発”を逃さないための備えが必要です。今回は、特に「リセッション中のインデックス投資」で重視すべきポイントを整理します。
1. リセッションでは何が起こるか?
景気後退期には、売上の減少、利益の圧迫、あるいは信用収縮が企業を襲います。例えば、長期金利が短期金利を上回る逆イールドは、銀行の貸出採算を悪化させ、経済の先行き懸念を示す典型的なシグナルです。Home+1さらに、過去の分析によれば、株式は景気サイクルのピークから数カ月後に下落に転じる傾向があり、経済活動よりも先行して動くケースが観察されています。capitalgroup.com+1
そのため、「リセッション期のインデックス投資=安心して放置」ではなく、“変化対応型”の運用マインドが求められます。
2. インデックス投資で注意すべき5つのポイント
ここからは、リセッション局面で特に意識すべき注意点を整理します。
(1) ポートフォリオの質を再確認
リセッションでは「借入が多い」「景気循環に左右されやすい」企業が特に弱くなります。Investopedia+1インデックスファンドであっても、構成銘柄のクオリティ(財務健全性、キャッシュフローの安定性)を意識しておきましょう。大型・安定系、ディフェンシブな業種(生活必需品、通信、公益)などへの比率が相対的に優位な時期です。Charles Stanley+1
(2) タイミング「だけ」で動かない
「景気後退入りだから売る」「反発し始めたから買い増す」といったタイミング狙いには大きなリスクがあります。Charles Stanley+1特にインデックス投資の場合、売却・再投資を繰り返すことはコスト・タイミング・税制面で負荷になりやすい。むしろ、月々一定金額を淡々と積み立てる“ドルコスト平均法”という習慣を守ることが、結果的に実践的といえます。
(3) リバウンドの「稲妻」を捉える準備を
リセッション期には、見えないところで“底打ち”を経て株価が急反発に転じるケースもあります。capitalgroup.com+1株価のサイクルは、経済指標より先に動くことが多く、経済活動が最悪期を迎える前、あるいその直後に上昇を始めることもあります。つまり、「リセッション中だから低迷し続ける」わけではないのです。インデックス投資家としては、底値での買い逃しを防ぐため、現金比率・積立額、買いタイミングの備えを検討すべきです。
(4) 分散と資産バランスの再点検
景気後退期こそ「分散」が効く局面です。株式だけで構成されたポートフォリオでは、影響を受けやすくなります。Charles Stanley+1債券、現金、金(ゴールド)などリスクヘッジの手段も考慮し、資産バランスを見直す機会としましょう。
(5) 自己資金の安全性を最優先に
リセッションで最も恐れるべきは「収入減」「失業」など運用以前のリスクです。Charles Stanley+1積立投資を行う上でも、無理な金額ではなく、生活防衛資金(3〜6か月分の生活費)を確保してからという基本が揺らいではなりません。
3. “一瞬の稲妻”を逃さない実践ステップ
投資家として、リセッション期に「待ち」「備え」「反撃」に移るために、次のステップを実践しましょう。
- 積立ルールの見直し
- 毎月の積立額を維持。株価が下落しても淡々と買える仕組みをつくる。
- 積立を一時停止するなら、明確なルールを決めておく(例:失業・収入激減時)。 - 買い増し余力の確保
- リスク許容度に応じて、積立以外に「チャンス時の追加買い」用の余剰資金を確保。
- 株価が明確に反発転じたと感じられるサインが出た際、少額でも追加投入。 - チャート・指標のチェック
- 株価の底打ちサイン(出来高増、逆イールドの改善、消費者信頼感回復など)に注目。russellinvestments.com+1
- 逆イールドの改善・景気先行指数の底打ちなど、リセッション懸念ピークの可能性がある場面を見極める。 - 売却ではなく“持ち続けること”を優先
- 反発期に売却してしまうと、その「一瞬の稲妻」を取り逃す可能性が高まります。むしろ、反発局面では“戻りの利益”を取りに行くのではなく、将来の成長余地を信じて保有を続けるほうが歴史的に成績が良いことが示されています。capitalgroup.com+1
4. よくある誤解とその対策
- 誤解①:リセッション=株価はずっと下がる
→実際には、株価のピークと景気のピークには時間差があり、景気が底打ちする前に株価が反発することもあります。capitalgroup.com+1 - 誤解②:インデックスだから何もしなくて良い
→基本方針は変わりませんが、運用環境が異なるため“何もしない”でも良いという訳ではなく、資産配分・積立ルール・心理準備が重要です。 - 誤解③:底値を正確に予測してから買うべき
→市場のタイミングを正確に当てるのは困難です。むしろ“投入を続ける”“リバウンドに備える”ことが現実路線です。Charles Stanley+1
5. まとめ:備えと反撃を同時に
リセッションという言葉は、投資家にとって恐怖とチャンスの両面を携えています。インデックス投資家であっても、景気後退期には以下を再確認しましょう。
- 財務健全な企業主体のインデックスであるか
- 毎月の積立を継続できる体力(資金余力・生活防衛資金)を有しているか
- 分散・資産バランスが適切か
- “一瞬の稲妻”=急反発に備える余力があるか
- 市場タイミングを追いかけず、持ち続ける意思を持っているか
リセッションが本格化すれば株価の下振れもありえますが、過去のデータでは「株式市場の底打ち・反発は景気の最終局面またはそれを追う形で訪れている」ことが示唆されています。capitalgroup.com+1つまり、恐怖に身を委ねるのではなく、「備え」と「反撃」の両輪で、長期視点のインデックス投資をリセッション期にも有効に機能させましょう。
最後に、投資は自己責任です。ご自身のリスク許容度、資金余力、家計の状態を踏まえ、冷静に判断・行動されることをお勧めします。


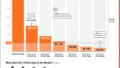
コメント