「年金はいつからもらうのが得か?」
多くの人が気になるテーマですが、これは単なる損得計算の問題ではありません。
実際には、平均寿命と中央値の差、そして「働けるかどうか」「どのように老後を過ごしたいか」といった人生観が大きく影響します。
この記事では、60歳からの繰り上げ受給と70〜75歳までの繰り下げ受給を比較しながら、大学生にも理解できるように「数字」と「生き方」の両面から解説します。
年金制度の基本:繰り上げと繰り下げ
- 繰り上げ受給(60歳〜)
1か月早めるごとに0.4%減額(60歳開始なら最大24%減額) - 本来受給(65歳)
標準的な開始時期 - 繰り下げ受給(70歳〜75歳)
1か月遅らせるごとに0.7%増額(75歳開始なら最大84%増額)
👉 制度的には「繰り下げ推奨」ですが、実際の判断には寿命が大きく関わります。
損益分岐点はおよそ81歳
例:
- 60歳から受給した場合 → 65歳から受給するより早く総額が増えるが、81歳で逆転される
- 70歳や75歳まで繰り下げる場合 → 長生きすればするほど有利
つまり、81歳を境に「繰り上げ有利 → 繰り下げ有利」へ切り替わるわけです。
平均寿命と中央値の違い
ここで重要なのが 平均寿命と中央値の差 です。
- 日本男性の平均寿命:約81歳(厚労省データ、2025年時点)
- しかし「中央値寿命」(50%の人が亡くなる年齢)は、平均よりやや低く、75〜77歳程度と推定されます。
👉 つまり「半分の人は75歳前後までに亡くなる」ため、繰り下げ戦略が必ずしも報われるわけではありません。
損得を超えた「生き方の選択」
数字だけで判断すると「中央値を意識して早めにもらった方が安全」に見えます。
しかし人生は損得計算だけではありません。
- 健康の維持:働き続けることで体力・脳機能を保てる
- 社会とのつながり:就労は孤立や認知症リスクを減らす
- 自己効力感:「まだ誰かの役に立っている」という実感
- リスクヘッジ:長生きしたときに備えて年金額を増やす
👉 年金は「収益商品」ではなく「長生きリスクに備える社会保険」だと捉えると、繰り下げも合理的です。
大学生への示唆
これから社会に出る世代にとって大切なのは、
「年金の損得ではなく、どんな働き方・生き方を選ぶか」 です。
- 「自由時間を早く得たい」 → 60歳で繰り上げもあり
- 「長寿リスクに備えたい」 → 70歳以降まで繰り下げも合理的
- 「健康で働き続けたい」 → 65歳以降に受給しつつ就労継続
つまり、「損得」ではなく「ライフデザイン」が判断の軸になります。
まとめ
- 60歳開始と65歳開始の損益分岐点はおよそ81歳
- 平均寿命は81歳だが、中央値は75歳前後 → 長生きできるかは未知数
- 年金は「保険」的な制度であり、単なる投資商品ではない
- 最適解は「自分の健康状態・働き方・価値観」で決めるべき
👉 年金のもらい方は「損か得か」ではなく、「どう生きたいか」の問題。
働けるうちは働き、社会とのつながりを持ちつつ、自分に合った受給時期を選ぶことが最も合理的です。
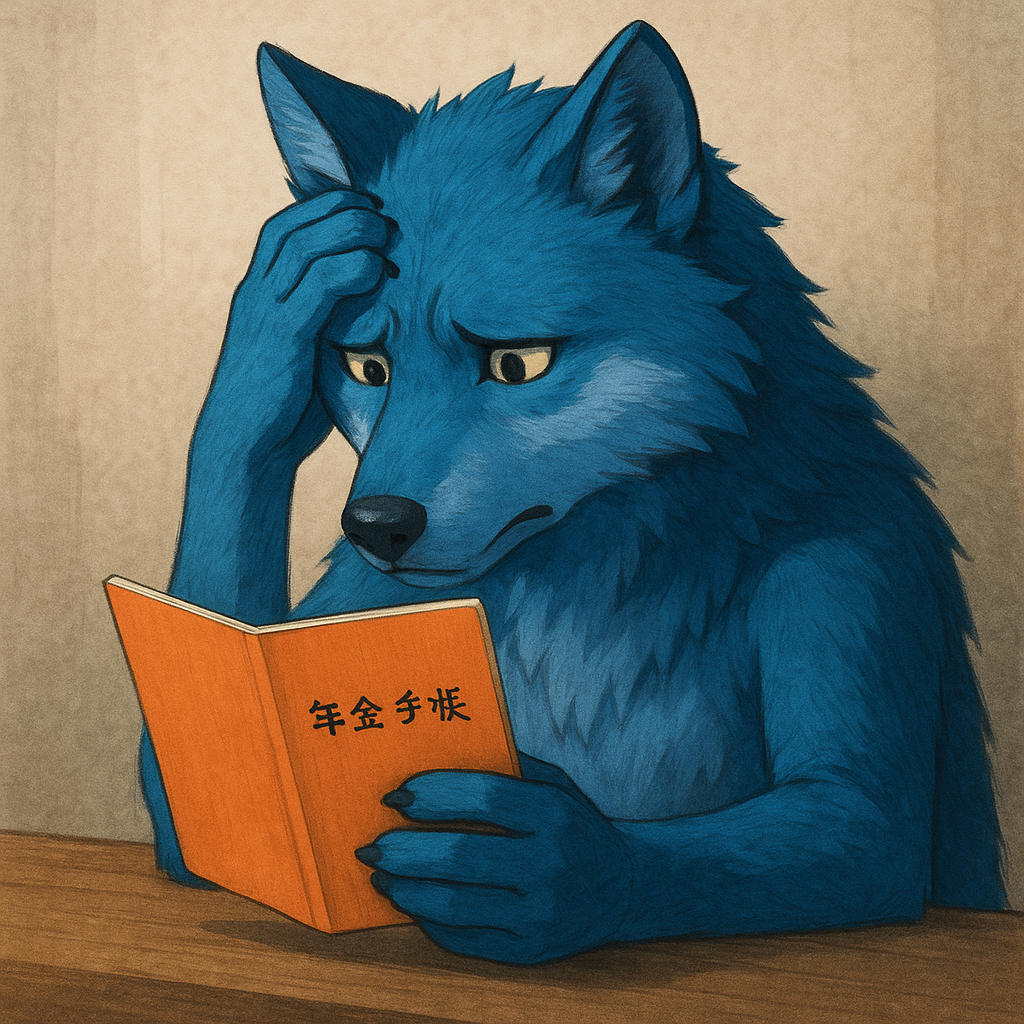



コメント